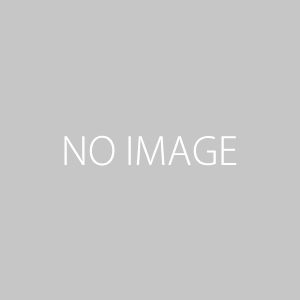亜鉛を使った新しい蓄電池、燃料電池の研究を行っている小川准教授
再生可能エネルギーの利用拡大に不可欠とされる蓄電技術。公立諏訪東京理科大学(長野県茅野市)機械電気工学科の小川賢准教授(43)は、自然の中で分解される部材を使った蓄電池の研究に取り組んでいる。電力会社の送電網につながっていない環境で、人が現場に定期的に足を運ばなくても電気をつくり、ためて、利用し続ける循環の構築を目指す。亜鉛と活性炭が主な部材で壊れても環境負荷が小さく、やがて自然に返る設計だ。
自然に返る蓄電池は正極(+)を活性炭と植物の細胞壁の主成分であるセルロース、負極(-)を亜鉛とセルロースで構成し、正極と負極が触れるのを防ぐセパレーターには木材や草などから抽出した繊維のパルプを原料に製造したフィルムを使っている。電解液はアルカリ性の水。電池の箱も間伐材を利用すればすべて自然由来の部材で構成された蓄電池ということになる。
主流のリチウムイオン電池と比べると、製造環境を整備する費用が安い。過充電や過放電、外部からの衝撃、セパレーター不良などによる電池内部の不具合が原因でショートした場合、リチウムイオン電池は発火する恐れもあるが、亜鉛蓄電池のショートによる熱は100度を超えることはまれという。
小川准教授はさらに水素ではなく、亜鉛を燃料とする燃料電池システムの研究にも取り組んでいる。水素と酸素で電力を生み出し、水を排出する燃料電池車は二酸化炭素を出さない環境に優しい自動車として普及に向けた課題解決が国レベルで進められている。
そうした中、小川准教授は燃料を水素から亜鉛に変える研究に取り組む。可燃性の水素よりも安全に貯蔵でき、発電に必要な化学反応を促す触媒もプラチナなどの希少金属ではなく、導電性カーボンで可能。排出される酸化亜鉛を再生可能エネルギーの電気で再び亜鉛に還元、亜鉛燃料電池の燃料として再利用できる可能性もある。
研究を進めるとともに企業との連携による実用化の可能性も探る同准教授。「電力会社に頼らずに電力を自給自足することにつながる技術。亜鉛を新しいエネルギー媒体とする研究を進めていく」と話す。
[/MARKOVE]